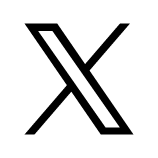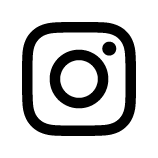日吉歯科診療所にみる、アート思考の予防歯科
―クラフトを否定し、サイエンス×アートで立ち上がった稀有なモデル
コンサルティング産業も予防歯科も、その成熟のプロセスは不思議なほど似ている。いずれも「クラフト(職人芸)」の時代から始まり、やがて「サイエンス(科学)」を経て、最終的には「アート(美意識)」の段階へと移行する。ここでいうアートとは、科学を患者や顧客の体験に変換し、行動変容を促す仕組みそのものを指す。
マッキンゼーを近代化したマービン・バウアーは、コンサルティングを経験則のクラフトから、データと論理に基づくサイエンスへと引き上げた。日本の予防歯科においては、熊谷崇先生が同じ役割を果たした。経験則的な処置中心から、エビデンスに基づく予防体系へ。どちらも産業全体の価値基盤を刷新した点で重なる。
だが、論理や科学だけでは限界に直面するのもまた同じだ。複雑な現代社会では、顧客や患者の感性に訴えかけるアートの要素が重要な競争資源となる。マッキンゼーが科学を超えて「ストーリー・テリング」や「体験デザイン」を重視するようになったのと同様、予防歯科もまた空間デザインや患者体験を重視する時代に入った。
この一般的な成熟プロセスを飛び越え、科学とアートを同時に実装したのが日吉歯科診療所である。1990年代、日本の予防歯科がまだクラフトの段階にあった時代に、日吉はサイエンスを導入すると同時に、患者体験としてのアートを設計した。ここにこそ、その稀有な先進性がある。
クラフトからサイエンスへ
コンサルティングの黎明期は「経験豊富な人物が勘や人脈を頼りに助言する」クラフトの時代だった。日本の予防歯科も同じで、歯科衛生士が「とりあえずブラッシング指導をしてみる」段階。効果測定はなく、方法も標準化されず、成果は医院ごとにばらついた。
マッキンゼーはこの状態を「ファクトベース」へと引き上げた。同じく日吉歯科は、PCR、BOP、PPDなど客観的指標の導入、唾液検査やカリオグラムによるリスク評価、10枚法X線や12枚法写真による可視化、OHIとSPTの標準化を進め、予防を「感覚」から「科学」へと昇華させた。
この転換は、日本の予防歯科をクラフトからサイエンスへと移行させる歴史的必然であり、熊谷先生の先見性と実行力の結晶だった。MTMは「時代の必然と個人の意志が結晶化した集大成」であり、日吉はその象徴的拠点となった。
MTMを継続・発展させるための選択と決断
サイエンスをアートへ ― ハイブリッド三本柱
しかし日吉の真の革新は、科学的データを単なる診断で終わらせず、患者が明快な理解、深い納得、そして行動を呼び起こすアートへと変換した点にある。ここにコンサルティングとの比較が活きる。データ分析を「戦略」に留めず、経営陣や社員が共感し行動に移すために「ストーリー化」するプロセス。日吉はそれを医療で実現した。
その仕組みが「ハイブリッド三本柱」である。
- OHI:数値を行動に翻訳する。PCRやBOPというサイエンスを、患者の生活習慣に落とし込み、日常行動へと変える翻訳装置。
- カリオグラム/OHIS:科学的根拠に基づくリスクデータを物語に翻訳する。むし歯や歯周病のリスクをグラフやビジュアルで提示し、患者を「治療される対象」から「自分の健康物語の主人公」へと変容させる。
- レントゲン/口腔内写真:科学を映像体験に翻訳する。客観的データを患者が「自分の口を見る」体験に変え、感情と行動を動かす。
これらはすべて「サイエンスを患者体験に変える」仕組みであり、日吉は科学的予防を「文化としての予防体験」へと昇華させた。
アート思考の三本柱 ― 患者の権利と責任
さらに日吉は、制度や外部認証ではなく、患者自身を最大の第三者認証者と位置づけた。ここに「アート思考の三本柱」がある。
- 患者との深い関係性の構築
患者には公正で良質な医療を受ける権利と、正確な情報をもとに家庭療法(セルフケア)を実践する責任がある。小児・成人ごとに担当衛生士を配置し、継続的に経過を把握する仕組みを制度化したのは、その責任を診療所が担うためである。 - 空間と体験のパーソナライズ
個室設計や自然光を活かした空間、国際水準の機器の導入は、プライバシーを守り安心して治療を受ける権利を具体化した。同時に患者には、診療所内で他者に配慮する責任がある。日吉は外部認証ではなく、日常診療を通じて得られる患者からの信頼を最高の認証とした。 - ストーリーの創造
「酒田市民の口腔健康を世界一に」という理念のもと、患者は意見を述べる権利と、定期メインテナンスや患者セミナー参加の責任を負う。診療所は連携や研修受け入れ、事故時の謝罪と再治療を担う。その三者が重なったとき、患者は“治療される存在”から“健康物語の主人公”へと変わる。
この三本柱により、日吉は患者の権利・責任・診療所の責任を明示し、信頼に基づく医療を文化として根付かせた。
制度を超える分岐点
ここまでを整理すると、予防歯科の進化は二段階で捉えられる。
- サイエンス段階:予防を医療として成立させることが目的であり、保険か自費かは副次的テーマだった。
- アート段階:どの体験に価値を見出すかという価値の論理が前面に出て、初めて保険・自費の選択が意味を帯びる。
日吉が示したのは、このアートのレイヤーに立ってこそ制度論が意味を持つという事実だ。患者は制度に従属するのではなく、自ら選んで制度を超えていける。
MTMイズムの継承と未来
今日、多くの歯科医院が「予防をやっている」と言えるのは、これは、MTMが提示した仕組みと理念が一定の影響を及ぼした結果であり、予防が医療として広く認知されるようになったことを示している。しかし制度が普及すればするほど、理念が希薄になり、予防が「手間のかかるルーティン」に堕する危険もある。
現在は、SPTや歯周病重症化予防治療(P重防)など制度の範囲が広がり、保険診療の中でもアート思考の予防歯科を実現できる環境が整いつつある。だがそれは、イズムを持った歯科医師・歯科衛生士が主体的に運用する場合に限られる。 制度が枠組みを提供しても、その価値を生きたものにするのは現場の意識と哲学である。
MTM継承の核心は「How」や「Know-How」ではなく、「Why」に立ち返ることだ。なぜこの方法で、なぜこの検査を、このタイミングで行うのか。その答えは、患者を健康物語の主人公に変えるというイズムにある。
ここで再びコンサルティングとの比較が有効だ。データ分析や戦略策定だけでは企業は変わらない。組織の物語を再構築し、人が動く仕組みに落とし込んで初めて変革が成立する。予防歯科も同じだ。制度の管理医療の枠内では不十分で、患者の尊厳を中心に据えるアート思考こそがイズムを生かす。
公的保険制度は最低限の医療を公平に提供する一方で、MTMの全人的アプローチを制限する壁にもなる。保険診療は治療(Repair)、自由診療は予防と最適化(Prevention/Optimization)を担い、本来は対立せず補完すべきもの。その狭間にこそ、制度ではすくいきれない「患者そのものへの敬意」があり、これこそがMTMの核心なのだ。
そして、この敬意に基づいて制度を超えて医療を実践することこそが、医療者にとってのやりがいであり、同時に大きな責任でもある。
予防歯科を次のステージへ
コンサルティングと予防歯科は、ともにクラフトからサイエンス、そしてアートへと成熟してきた。だが日吉歯科診療所は、その一般的プロセスを超え、サイエンスとアートを同時に実装した稀有なモデルである。
「ハイブリッド三本柱」と「アート思考の三本柱」によって科学を患者体験に変え、患者の権利と責任を明確化し、予防を制度の管理から解放した。その哲学は、コンサルティングが科学とアートを統合して企業変革を成功させるのと同じ構造を持っている。
予防歯科の未来は、技術ではなくイズムの継承にかかっている。日吉が示したのは、制度を超え、患者を中心に据えた「アート思考の医療」が、日本の予防歯科を次のステージへ導くという事実である。
CRECER/JOF 伊藤