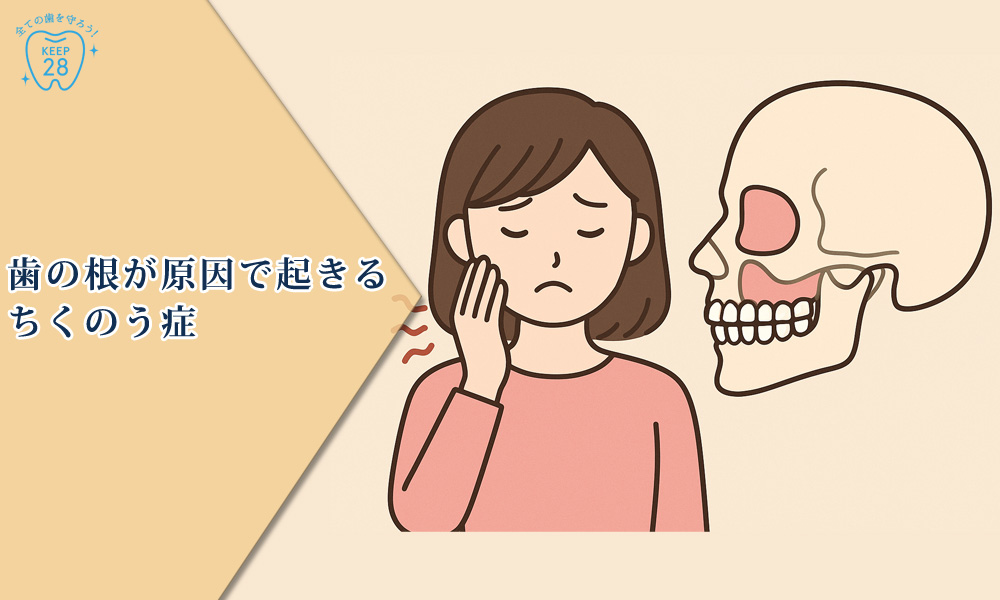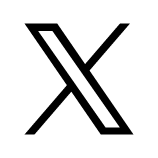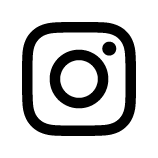歯の根が原因で起きるちくのう症
「歯の神経を取るということ」 に、歯の神経、つまり歯の内部にある柔らかい組織(歯髄)を取ると、歯の寿命が短くなりがちであることを説明しました。歯髄を取った歯の根に行う治療(根管治療)を行った後に続く厄介な問題がまだあります。
その一例が、専門用語で「歯内由来の上顎副鼻腔炎(Maxillary Sinusitis of Endodontic Origin: MSEO)」というものです。これは2018年、米国歯内療法学会により公式に命名され、他の原因による副鼻腔炎と区別されるようになりました。
そもそも副鼻腔炎とは、鼻の周囲にある空洞(副鼻腔)がウイルスや細菌に感染して炎症を起こす病気で、日本では「ちくのう症」という名称の方が馴染み深いかもしれません。主な症状は、鼻づまり、鼻水、顔面の痛みや圧迫感などです。まれに重症化すると眼窩蜂巣炎、失明、髄膜炎、脳膿瘍といった深刻な合併症に至ることもあります。
副鼻腔のうち「上顎洞(じょうがくどう)」は、上の奥歯の根元と非常に近接した位置にあります。顔が小さな方の場合、上顎洞の底部の形が歯の根の周囲を取り囲むように入り組んでいることもあります。そのため、歯の細菌感染、根管治療、根の破折、抜歯、歯の位置異常などによって上顎洞の粘膜に炎症が波及することがあるのです。世界中の論文を調査した結果、副鼻腔炎の約半数がこのような歯を原因とするものであることが明らかになっています。
なかでもMSEOは根管治療に続いて起こる副鼻腔炎に限定されます。発端は小さなむし歯や歯周病です。それが歯髄にまで達すると、根の先に炎症が広がることがあります。歯髄が侵されると激しい痛みを伴うため、通常は根管治療が行われますが、この処置はいつも成功するとは限りません。治療が不完全だった場合も歯の根の先に炎症が広がることがあります。上の奥歯の場合は、その先の上顎洞を囲う粘膜まで炎症がおよび、上顎洞にまで波及して膿がたまることがあるのです。このようなMSEOの特徴は片側だけに起きることです。
MSEOに対して耳鼻科で副鼻腔炎の治療を受けても、原因である歯の病気が残っている限り完治しません。この病気の治療においては、歯科と耳鼻科の連携が不可欠です。MSEOに対しての治療はまず原因となっている歯の処置から。それには次の4つがあります。
- 根管治療(歯の神経と根の中の感染物質の除去)
- 根の先端部分の手術(顎の骨からアプローチし、根の先端の感染部位を除去)
- 意図的再植(一度歯を抜き、外で清掃処置後に再び戻す)
- 抜歯(歯の保存が不可能な場合)
また、抗生物質を服用することもありますが、これはあくまでも症状を一時的に緩和するための補助的な手段であり、根本治療ではありません。
これらの歯科的処置でも症状が改善しない場合、耳鼻科で副鼻腔の外科的処置(手術)が検討されます。なお、歯科と耳鼻科が同時に処置を行うのは、重度かつ急性の症例に限定して検討されるべきとされています。
健康な歯髄からMSEOが発症することはありません。ご自身でコントロールできる段階で、むし歯と歯周病をしっかりと予防することを何よりお勧めしたいです。
画像説明
歯の問題が、ちくのう症になるなんて…
Illustration by ChatGPT
参考文献
- American Association of Endodontists. AAE position statement. Maxillary sinusitis of endodontic origin. 2018. p. 1–11. Available at:
- 日本歯内療法学会による和訳. 歯内起源の上顎副鼻腔炎
- Vitali FC, Santos PS, Massignan C, Maia LC, Cardoso M, Teixeira CDS. Global Prevalence of Maxillary Sinusitis of Odontogenic Origin and Associated Factors: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Endod. 2023 Apr;49(4):369-381.e11.
筆者プロフィール
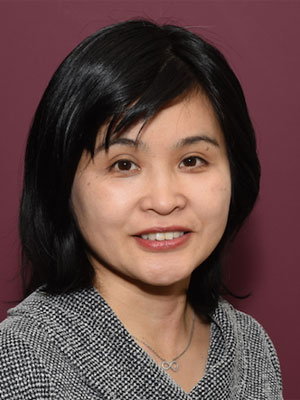
Makiko NISHI
西 真紀子 NPO法人「科学的なむし歯・歯周病予防を推進する会」(PSAP)理事長
(旧称 「最先端のむし歯・歯周病予防を要求する会」)
| 1996年 | 大阪大学歯学部卒業 |
| 大阪大学歯学部歯科保存学講座入局 | |
| 2000年 | スウェーデン王立マルメ大学歯学部カリオロジー講座客員研究員 |
| 2001年 | 山形県酒田市 日吉歯科診療所勤務 |
| 2007年 | アイルランド国立コーク大学大学院修士課程修了 |
| Master of Dental Public Health (MDPH)取得 | |
| 2010年 | NPO法人「科学的なむし歯・歯周病予防を推進する会」(PSAP)理事長 |
| (旧称 「最先端のむし歯・歯周病予防を要求する会」) | |
| 2018年 | 同大学院博士課程修了 |
| Doctor of Philosophy(PhD)取得 |